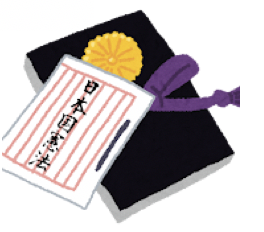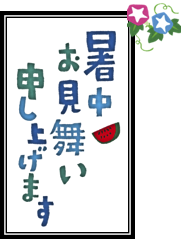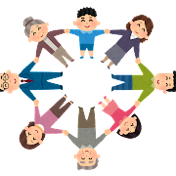不動産登記簿には、所有者の氏名や住所が記載されていますが、土地の相続などの際に所有者について登記が行われないなどの理由で所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても所在不明で連絡がつかない土地が大きな問題となっています。
不動産登記簿には、所有者の氏名や住所が記載されていますが、土地の相続などの際に所有者について登記が行われないなどの理由で所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明しても所在不明で連絡がつかない土地が大きな問題となっています。
所有者が不明の土地の面積は、国土の22%に上るそうで(九州よりも広い!)、公共事業を妨げたり、管理が不十分なため、近隣に悪影響を及ぼすなどの問題が発生しています。
所有者不明土地の発生予防のために、民事基本法制の見直しがなされましたが、今回は、その中でも、多くの方に影響がある相続登記の申請義務化についてご紹介します。
1 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます!
相続によって不動産を取得した場合、現在は、不動産の相続登記の申請は義務ではありません。令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されることとなります。
相続が発生した時に、遺言がある場合や、ない場合、相続人が複数いる場合や一人しかいない場合などで、遺産分割の話し合いが必要なのかどうかが変わります。
遺言があれば、遺言により不動産を取得した相続人が、相続登記の申請を行うことになります。遺言がない場合でも、相続人が一人しかいない場合は、不動産を単独で取得した相続人が相続登記を行うこととなります。そして、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
2 遺言がない場合で、相続人が複数いる場合はどうなる?
相続人全員で、遺産分割の話し合いを行うこととなりますが、遺産分割が3年以内に成立するかどうかによって、登記申請の内容が変わってきます。
3年以内に遺産分割が成立する場合は、3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、相続登記申請を行えばよいことになります。
これが難しい場合は、下記の遺産分割に時間を要するケースと同様の登記申請を行う必要があります。
3 遺産分割の話し合いに時間がかかりそう。相続登記の義務は免除される?
早期に遺産分割をすることが困難な場合は、「相続人申告登記」を、不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
「相続人申告登記」とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。また、登録免許税はかかりません。
相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能で、登記簿に氏名・住所が記録された相続人のみ、相続登記申請義務を履行したこととなる点に注意が必要です。
遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請を行う必要があります。もし、遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられません。
4 登記義務に違反すると、どうなる?
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
正当な理由の例として、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなどが想定されています。
5 過去の相続にも適用される?
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合についても適用されます。
令和6年4月1日か、相続によって不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要がありますので、ご注意ください。
6 相続のことについてわからないことは、どうぞご相談ください。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますので、遺産分割を行わず放っておくと、過料が科される場合がありますので、早めに遺産分割の話し合いを開始することをお勧めします。
もし、相続する意思がない場合は、そのままにしておかず、家庭裁判所にて、相続放棄の手続が必要となります(相続開始を知った時から3か月以内の期間制限にご注意ください)。
遺産分割の話し合いや相続手続には法的な知識が必要なことも多いので、わからないことがありましたら、どうぞご相談ください。









































 先日(7月3日)、最高裁判所で、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、国に賠償責任があるとする判断が確定したとして大きく報道されました。
先日(7月3日)、最高裁判所で、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、国に賠償責任があるとする判断が確定したとして大きく報道されました。